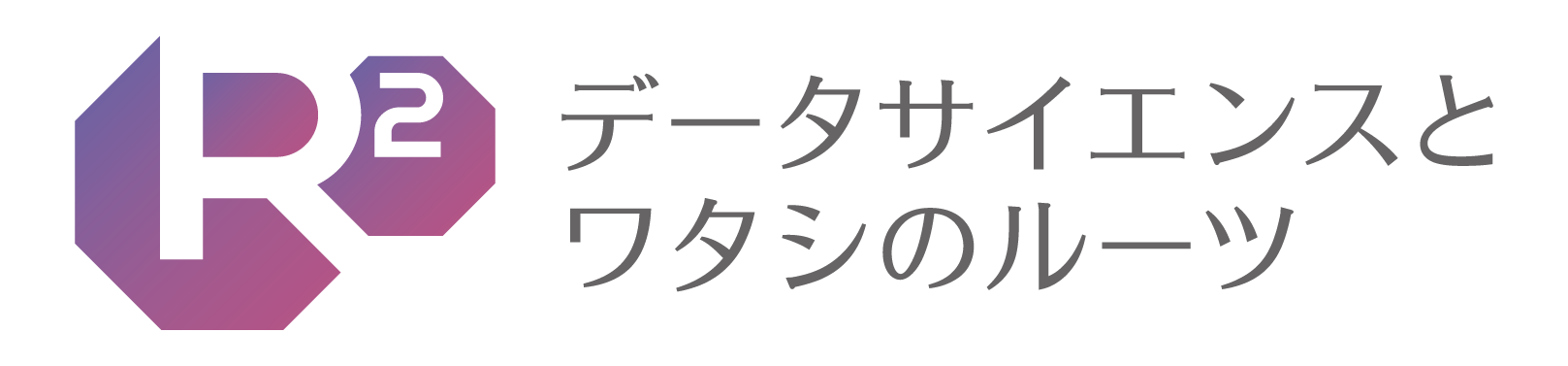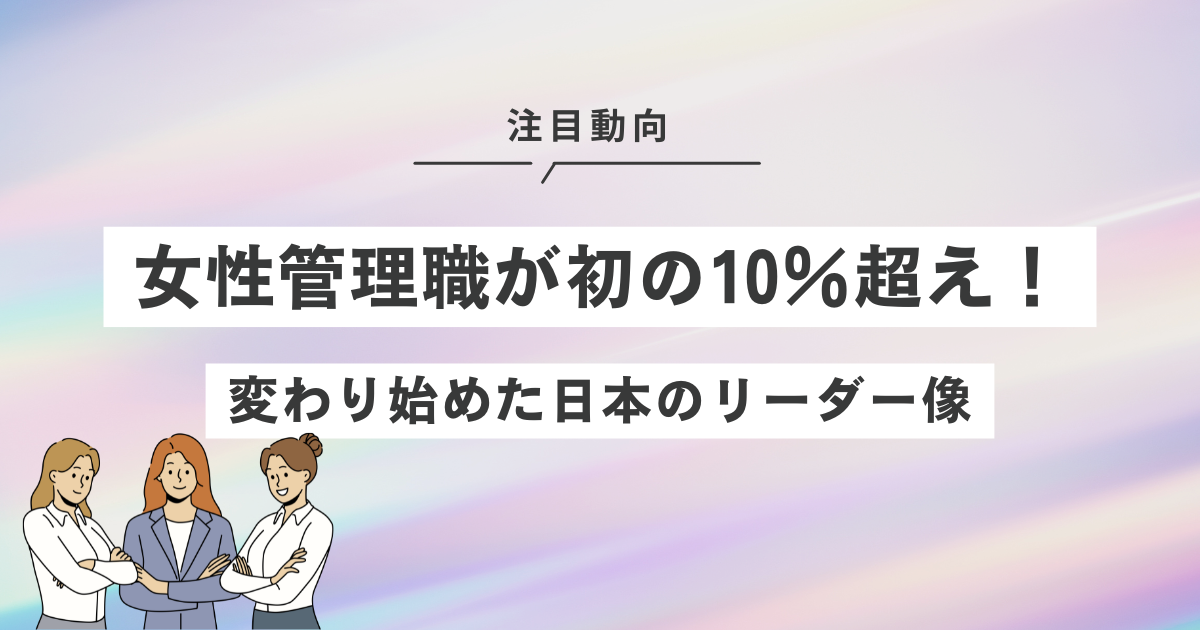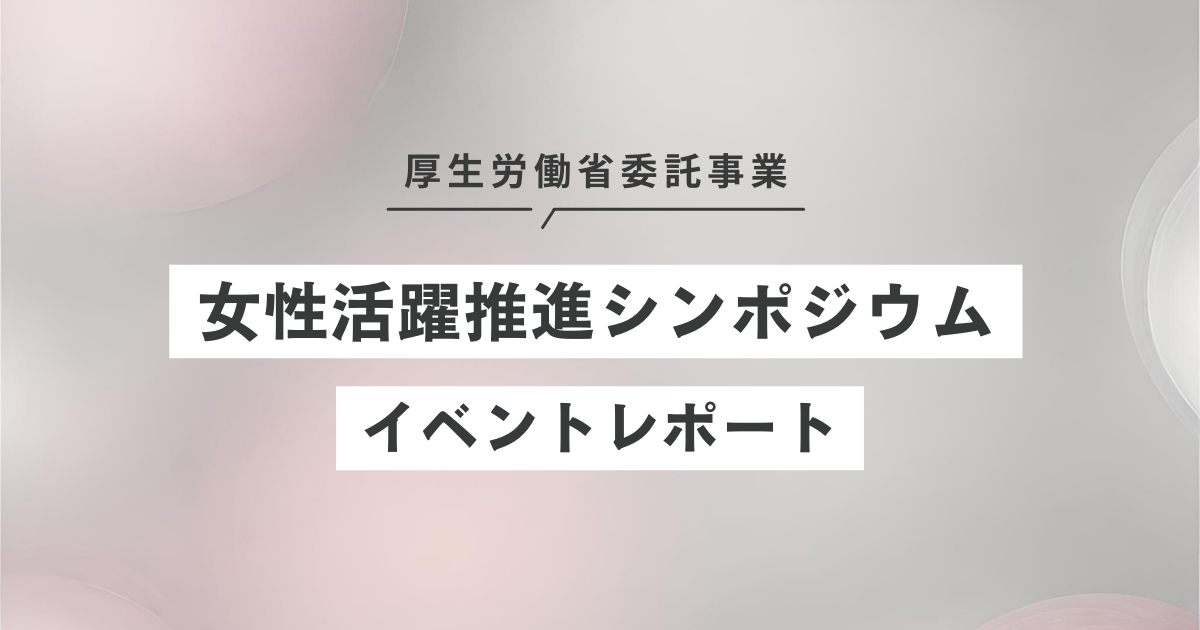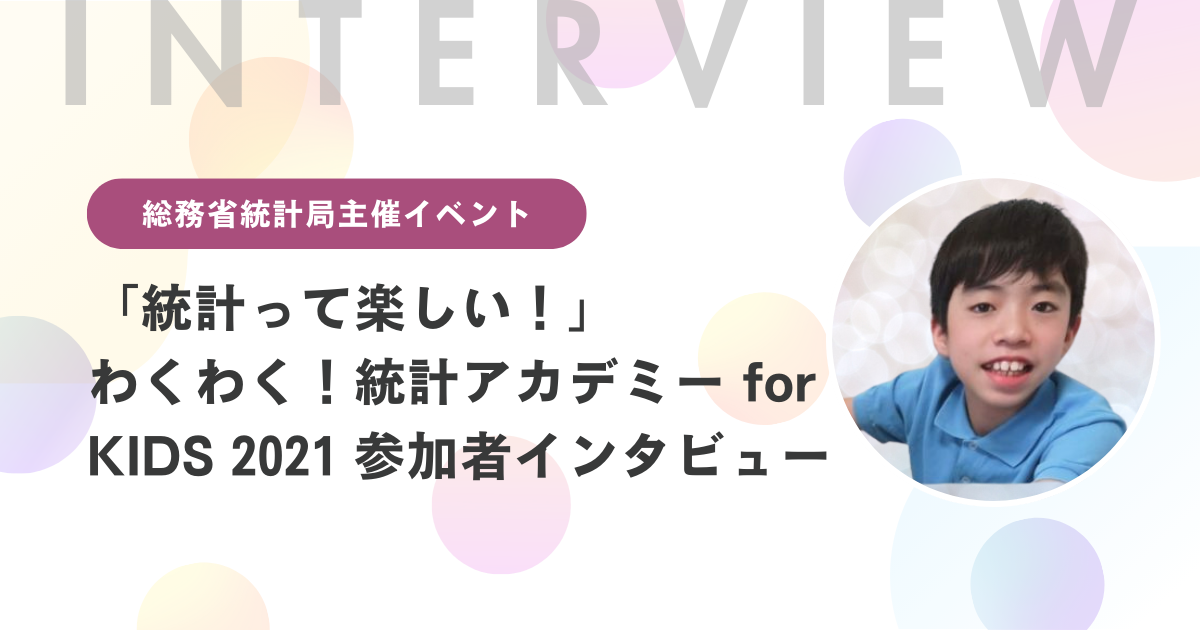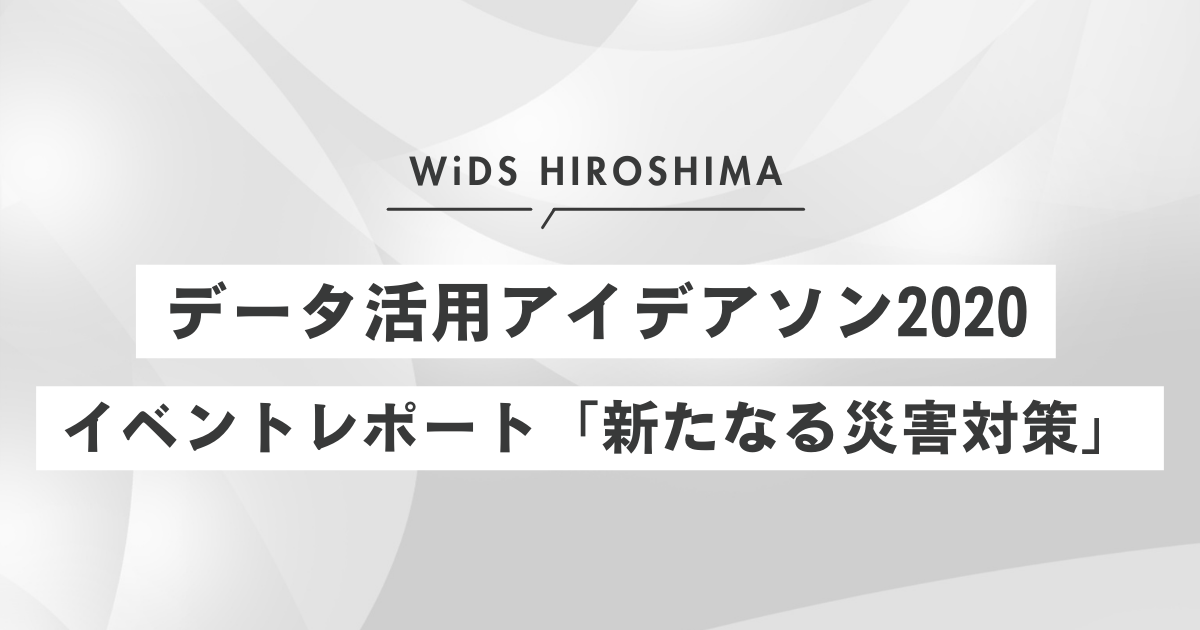はじめに
2025年3月7日、広島県内のデータサイエンス分野における重要なイベント「WiDS HIROSHIMA シンポジウム」が開催された。「やってみんさい!データサイエンス」を合言葉に、広島から始まるデータサイエンスの新時代を目指して開催された本イベント。女性の力で日本のデータ活用を加速させることを目指し、多くの参加者を集めた。
WiDS(Women in Data Science)は、2015年に米国スタンフォード大学を中心に始まったシンポジウムである。世界中の200以上の地域で開催されており、世界中どこからでも、性別を問わずに誰もが参加できる。AIやデータサイエンスの発展と、この分野での人材育成や女性の活躍推進を目的とした国際的な取り組みとなっている。
広島県は、西日本初の地域イベントとして2020年よりWiDS HIROSHIMA(ウィズひろしま)を開催している。広島県が独自に持つ教育の取り組みと、産業界の基盤を活かしたデータサイエンス人材の育成を目指し、この活動を普及してきた。特に注目すべきは、データサイエンスの領域は女性が少ないとされているが、実は女性の特性を生かせる分野であることを広く伝え、世代やジェンダーを問わず「データサイエンスって何だろう」と気になっている方々にデータサイエンスの魅力を伝えるイベントとして位置づけられていることだ。
本記事では、2025年のWiDS HIROSHIMAシンポジウムの様子を詳細にレポートし、各発表者の講演内容や議論のポイントを紹介する。データサイエンスが広島の未来をどのように変えていくのか、その可能性と展望について考察していきたい。
イベント概要
シンポジウムは、2025年3月7日(金)13:30から16:30まで、広島市中区に位置するHiromaLabを現地会場として開催された。会場参加は30名の定員制であったが、オンラインでの参加は制限なく、Zoomを通じて多くの参加者がバーチャルに集った。
イベントは広島県が主催し、「データで広島の未来をアップデート」というビジョンのもと、スポーツをはじめとする広島を支える分野を中心にデータ活用の可能性を紐解くことを目指した。参加費は無料で、ジェンダーを問わずデータサイエンスやデータ活用に関心がある方々を対象としていた。
プログラムは開会挨拶から始まり、関連イベントでデータサイエンスに初挑戦した参加者の体験談、スポーツ栄養とデータの可能性、ヘルスケアとデータサイエンス、そしてプロ野球とデータ分析に関する特別セッションまで、多岐にわたるテーマが取り上げられた。また、イベント終了後には現地交流会も開催され、参加者同士の交流を深める機会も設けられた。
このイベントの特徴は、データサイエンティストや自身の業務にデータを活用しているプロフェッショナルな女性陣が登壇し、実際の現場での挑戦や成功体験を通じて、キャリア形成や社会課題への具体的な取り組みを紹介したことにある。また、講演中に寄せられた質問に触れる対話型のセッションも設けられ、参加者との双方向のコミュニケーションが図られた。
アンバサダー紹介

WiDS HIROSHIMAのアンバサダーを務める菅由紀子氏は、株式会社Rejoui代表取締役であり、広島大学の客員教授としても活躍している。大崎上島町出身の菅氏は、瀬戸内海に浮かぶ美味しいレモンの産地で育ち、2016年9月に株式会社Rejouiを創立した。
企業におけるデータ×AI活用、同領域の人材育成を支援する活動を展開し、2019年には米国スタンフォード大学ICME発のデータサイエンス人材育成シンポジウム『WiDS』アンバサダーに就任した。
菅氏はデータ×AIに関する女性・若手人材育成にも尽力しており、WiDS HIROSHIMAを通じて産官学のデータサイエンス分野で活躍する女性データサイエンティスト達を中心に、広島県から次世代のデータサイエンティストを輩出することを目的に活動している。
今回のシンポジウムでは開会挨拶を担当するとともに、パネルディスカッションやプロ野球データ分析のセッションではファシリテーターとして議論をリードした。菅氏の熱意と専門知識は、イベント全体を通して参加者に大きな刺激を与え、データサイエンスの可能性を広く伝える原動力となっていた。
各発表者のレポート
データサイエンス初挑戦!離島 下蒲刈島での生成AI体験談
ダンス・ヨガ講師として活動するうららさんは、前年11月に行われたWiDS HIROSHIMAのバスツアー「下蒲刈島 1DAY データサイエンス」に参加した体験をもとに講演を行った。
フリーランスでダンスとヨガを通して幅広い世代やニーズに応じたサポート活動を展開してきたうららさんにとって、データサイエンスは全く新しい分野だったという。

講演では、生成AIを使った観光ポスター作成の工程、グループでの取り組み、そしてデータサイエンスに対する意識の変化などについて語られた。特に印象的だったのは、ダンスやヨガの指導という芸術的・身体的な活動と、データサイエンスという論理的・分析的な分野が、実は「人々の生活を豊かにする」という共通の目標を持っているという気づきだった。
うららさんは2011年からタウン誌を中心とした障害のある子どもたちへのダンスレッスンに携わり、2012年にはキッズヨガや健康美をテーマにしたヨガをスタート。幼稚園主催の親子ヨガや学校教員向けのメンタルヘルスケアなど、多様な活動を展開してきた経験から、データサイエンスの多様性推進と教育における可能性について独自の視点で語った。
参加者からは「専門家ではない視点からのデータサイエンス体験談が新鮮だった」「生成AIの実践的な活用例が参考になった」といった声が聞かれ、データサイエンスの裾野を広げるという点で大きな意義のある発表となった。
広島のスポーツを変える スポーツ栄養士からみたデータの新たな可能性
SHOKU LEAD代表であり公認スポーツ栄養士の馬明真梨子氏は、スポーツ栄養サポートで用いられる主な量的データと、サポートによって得られる質的データ、コンディションアプリの活用で得られるデータ解析の活かし方・見えることについて紹介した。
広島市佐伯区出身の馬明氏は、安田女子高校、県立広島大学卒業後、スポーツジムでの栄養・トレーニング指導業務を経て2014年に独立。現在は広島県を中心にアスリートの栄養サポート、スポーツ食育、商品監修・コンサルティング、健康経営、栄養士キャリアアップ事業等を展開している。
講演では、2023年よりスポーツ栄養サポートで得られたデータを活用した学会発表や論文執筆の経験を踏まえ、サポートの質の向上やスポーツ栄養士の価値・認知度向上に向けた取り組みについて語られた。
なかでも注目を集めたのは、広島のスポーツシーンにおけるデータ活用の具体的な事例紹介だった。

馬明氏は「データは単なる数字ではなく、アスリートの可能性を最大限に引き出すための重要なツール」と強調。栄養摂取データと競技パフォーマンスの相関関係や、長期的なコンディショニングデータの活用方法など、実践的な内容に参加者は熱心に聞き入っていた。
質疑応答では「一般の人でも活用できるデータ収集の方法はあるか」「子どものスポーツ活動にもデータ分析は有効か」といった質問が寄せられ、馬明氏は自身の経験を踏まえた丁寧な回答で会場を沸かせた。
ヘルスケアとデータサイエンス 広島県で働く女性の健康課題と対策について
一般社団法人ヘルスケアマネジメント協会代表理事の振本恵子氏は、日本における働く女性の健康に関するデータから対策について仮説を立て、広島県内の企業向けに施策を実施した結果から見えてきたことについて発表した。
看護師、看護教員、心理カウンセラーなどの経験を活かし、健康教育コンサルタントとして独立した振本氏は、健康経営社会の実現を目指し、2016年に一般社団法人ヘルスケアマネジメント協会を設立。代表理事として企業員の健康を支える健康管理体制づくりを支援し、経営課題の解決に繋げる活動を展開している。
講演では、女性特有の健康課題がワークライフバランスや生産性にどのような影響を与えるかについてのデータ分析結果が示され、それに基づいた具体的な対策の効果測定までが包括的に紹介された。
特に、月経関連症状や更年期症状などの女性特有の健康課題に対する職場での理解促進と支援体制の構築が、女性の活躍推進に直結するという振本氏の解説は説得力があった。

振本氏は「データは見えない課題を可視化し、効果的な解決策を導く羅針盤となる」と述べ、健康経営における女性視点の重要性を強調した。また、県立広島大学大学院保健福祉学専攻修士課程修了者として、学術的な視点からもデータの解釈と活用について言及し、参加者に新たな気づきを提供した。
質疑応答では、企業の健康経営担当者から具体的な施策の導入方法についての質問が多く寄せられ、振本氏の取り組みが実務レベルでも高い関心を集めていることが窺えた。
パネルディスカッション「データで見つける、ウェルビーイングのカギ」

休憩を挟んだ後、「データで見つける、ウェルビーイングのカギ」と題したパネルディスカッションが行われた。スピーカーには振本恵子氏と馬明真梨子氏が登壇し、ファシリテーターを菅由紀子氏が務めた。
このセッションでは、健康とデータの関係性について深く掘り下げられた。「私たちの生活に欠かせないこの2つはどのようにつながるのでしょうか?」という問いかけから始まり、スポーツと栄養、メンタルヘルス、そしてデータ活用という異なる専門領域を持つ3名の専門家が集まり、地域を起点としたウェルビーイングの可能性について語り合った。
特に注目を集めたのは、普段あまり意識することのない健康経営やデータ活用の取り組みが、私たちとどんな関わりを見せるのかという議論だった。心身と社会が共によい状態であるウェルビーイングを実現するためのヒントが、データの中に隠されているという視点は、多くの参加者に新たな気づきを与えた。
馬明氏からは「スポーツ栄養の分野では、データを活用することで個人に最適化されたサポートが可能になる」という実践例が紹介され、振本氏からは「健康データの蓄積と分析が、予防医療や健康経営の質を高める」という視点が示された。菅氏はこれらの意見を巧みに引き出しながら、広島という地域特性を活かしたデータ活用の可能性について議論を展開した。
参加者からは「異なる専門分野からのアプローチが刺激的だった」「データ活用の具体例が参考になった」といった声が聞かれ、分野横断的な議論の価値が再確認された。
特別企画「プロ野球ファン必見!データで語る球団の魅力」
シンポジウムの締めくくりとして、「プロ野球ファン必見!データで語る球団の魅力」と題した特別セッションが行われた。このセッションでは、フリーパーソナリティでカープ女子会リーダーの住本明日香氏と、株式会社NTTデータ コンサルティング事業本部の荒智子氏が登壇し、ファシリテーターを菅由紀子氏が務めた。
住本氏は小さい頃からラジオ好きで、”女子高生DJ募集”への応募がデビューのきっかけとなった。大学在学中は「アスカランド」というラジオ番組で4年間毎日担当し、その後もRCCキャスタードライバーを経て、ラジオ・テレビ・司会などの仕事に携わってきた。現在は母校の広島修道大学で非常勤講師を担当し、Facebookページで展開している「カープ女子会」でリーダーとしても活動している。
一方の荒氏は、入社以来、メディアやエンタメ業界における新規事業の立上げ等に従事し、2016年からはVRを利用したシミュレーションシステムを選手のパフォーマンス向上及びファンエンゲージメントの両面の目的で立ち上げた経験を持つ。NPB、MLB日米に向けた展開や、2022年からはプロ球団だけでなく、アマチュアチームや運動をするきっかけ作り、健康促進の目的を含めた幅広いサービス展開を行っている。

セッションでは、野球を統計学的に分析してチーム運営や戦略に役立てる「セイバーメトリクス」という分析手法が分かりやすく解説された。データ活用でスポーツの楽しみ方がどのように広がるのか、参加者と共に探求する内容となった。
住本氏はカープファンとしての視点から、データ分析が野球観戦の楽しみをどう広げるかについて語り、荒氏はXR技術をトレーニングやファンサービスに取り入れることで生まれる新しい体験について紹介した。両者の異なる視点からのアプローチが、スポーツとデータサイエンスの融合が生む新たな可能性を浮き彫りにした。
参加者からは「野球をデータで見る視点が新鮮だった」「カープファンとしても参考になる話が多かった」といった感想が寄せられ、データサイエンスの応用範囲の広さを実感させるセッションとなった。
イベントの特徴と成果
WiDS HIROSHIMA 2025シンポジウムの特徴は、データサイエンスという専門性の高い分野を、様々な角度から親しみやすく紹介したことにある。「やってみんさい!データサイエンス」というテーマ通り、初心者でも気軽に参加できるプログラム構成と、最前線で活躍するプロフェッショナルたちの実践事例を組み合わせることで、データサイエンスの裾野を広げる試みとなった。

参加者の多様性も特筆すべき点だ。会場には学生から社会人まで幅広い年齢層が集まり、オンラインでは広島県外からの参加者も多く見られた。特に女性参加者の割合が高かったことは、女性のデータサイエンス分野への関心の高まりを示すものと言えるだろう。
イベントを通じて、データサイエンスが単なる技術や学問ではなく、スポーツ、健康、エンターテイメントなど様々な分野と融合することで新たな価値を生み出すことが示された。特に広島という地域特性を活かしたデータ活用の事例が多く紹介されたことで、参加者にとって身近な課題解決の手段としてのデータサイエンスの可能性が実感できる内容となった。
イベント終了後に開催された現地交流会では、軽食と飲み物を用意し、参加者同士の交流が図られた。時間内の入退場に制限はなく、気軽に参加できる雰囲気が作られていた。この交流会では、講演者と直接対話する機会も設けられ、より深い議論や質問が交わされる場となった。
今後の展望
WiDS HIROSHIMAの活動は、単発のイベントにとどまらず、継続的な人材育成と地域におけるデータサイエンス普及を目指している。今回のシンポジウムを通じて得られた知見や人的ネットワークを活かし、今後も様々な取り組みが展開されることが期待される。
特に注目すべきは、広島県が西日本初の地域イベントとしてWiDS HIROSHIMAを位置づけ、産官学連携のもとでデータサイエンス人材の育成に取り組んでいる点だ。この取り組みは、地方創生やデジタルトランスフォーメーション(DX)の文脈においても重要な意味を持つ。
女性データサイエンティスト育成の観点からは、ロールモデルの提示と実践的な学びの場の提供が今後も継続されることで、データサイエンス分野における女性の活躍がさらに広がることが期待される。今回登壇した女性プロフェッショナルたちの活躍は、次世代の女性データサイエンティストにとって大きな刺激となるだろう。
また、「下蒲刈島 1DAY データサイエンス」のような地域に根ざした体験型プログラムの展開も、データサイエンスの裾野を広げる上で効果的なアプローチとして注目される。地域の課題解決にデータサイエンスを活用する実践的な取り組みは、学びの深化と地域貢献の両面で価値がある。
まとめ
WiDS HIROSHIMA 2025シンポジウム「やってみんさい!データサイエンス」は、データサイエンスの可能性を広く伝え、特に女性の活躍を促進するという目的を十分に達成したイベントだった。各発表者の多様な視点からのアプローチは、データサイエンスが様々な分野と融合することで生まれる新たな価値を示すものだった。
特に印象的だったのは、データサイエンスが単なる技術や学問ではなく、人々の生活を豊かにするツールとして位置づけられていたことだ。うららさんのダンス・ヨガの視点、馬明氏のスポーツ栄養の視点、振本氏のヘルスケアの視点、住本氏と荒氏のスポーツエンターテイメントの視点など、多角的な切り口からデータサイエンスの可能性が語られた。
「やってみんさい!」という広島弁のフレーズには、まずは試してみることの大切さが込められている。データサイエンスという一見敷居の高そうな分野も、実際に触れてみることで新たな発見や可能性が広がることを、このイベントは体現していた。女性の力で日本のデータ活用を加速させる取り組みは、今後も継続的に展開されることだろう。
WiDS HIROSHIMAの活動が、データサイエンス人材の育成と地域の発展にどのように貢献していくのか、今後の展開にも注目したい。